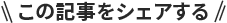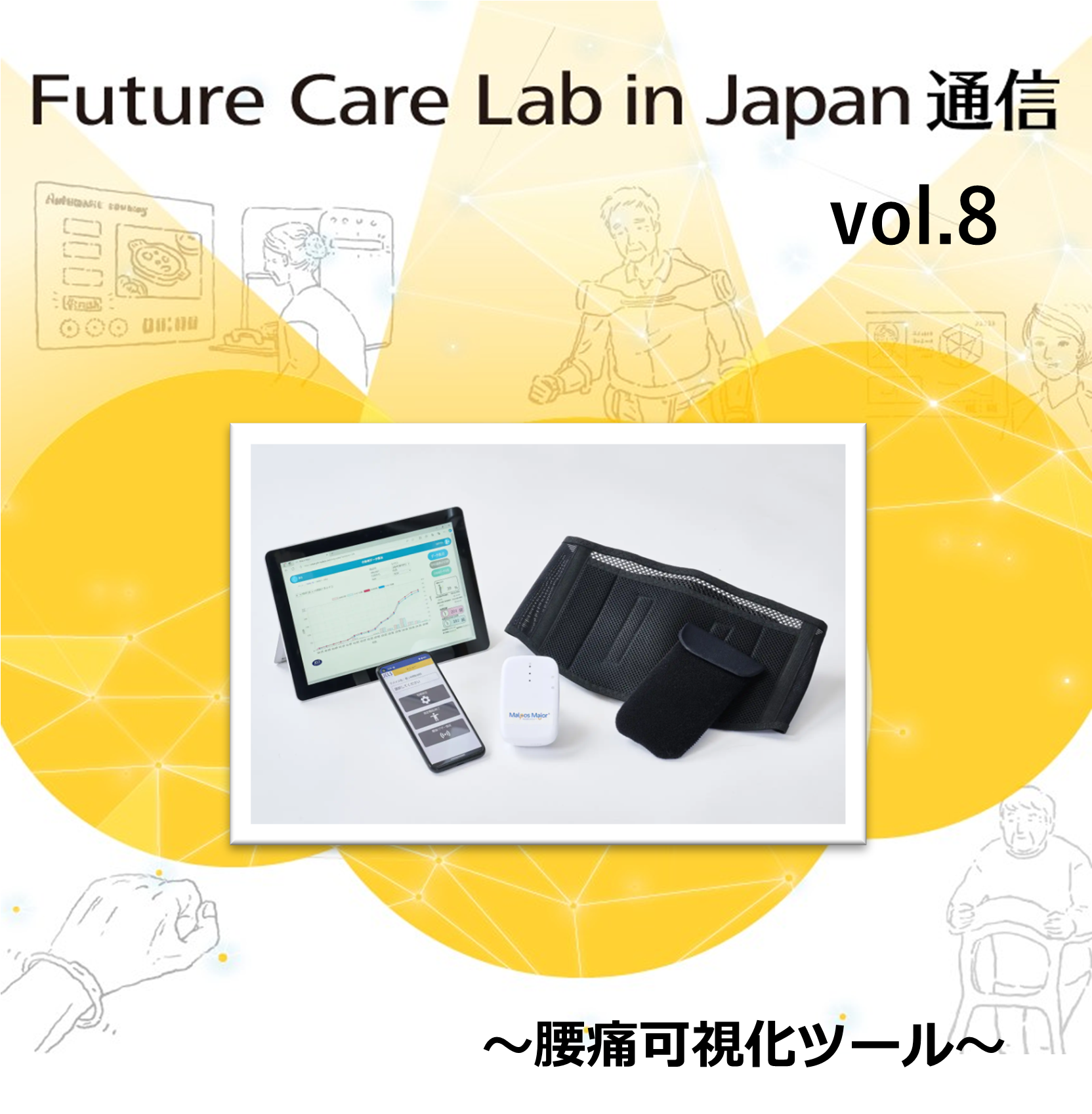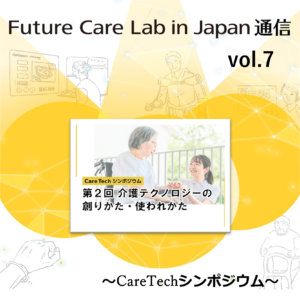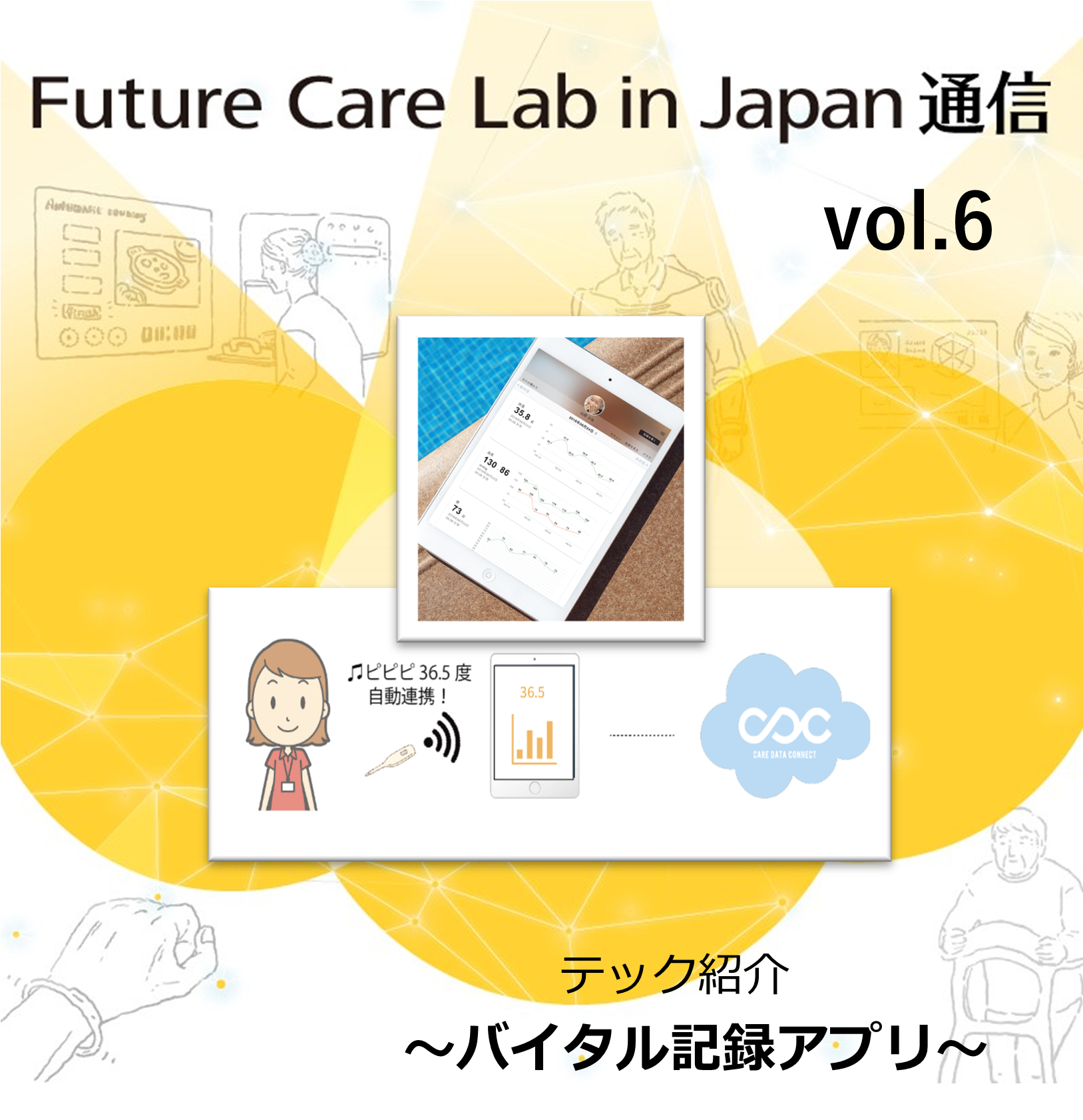Future Care Lab in Japan通信 Vol.7
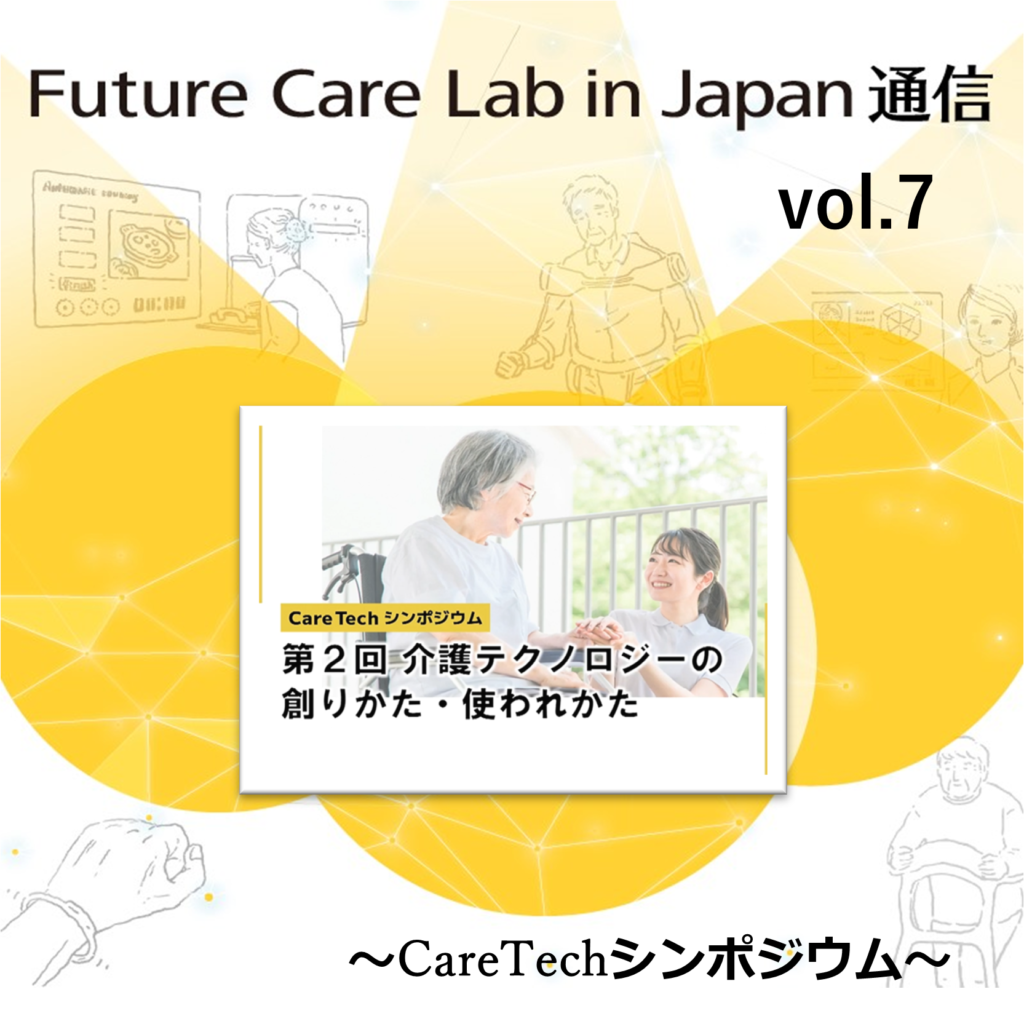
この連載ではFuture Care Lab in Japan(以下FCL)という研究所について、何を目指し、どんなことをしているのかをご紹介していきます。
第7回目は、FCL主催のCareTechシンポジウム開催『介護テクノロジーの作り方・使われかた』についてお届けします。
―目的―

このシンポジウムは、超高齢社会におけるシニア世代の暮らしに革新的な変化をもたらすスタートアップやベンチャー企業、新規事業で介護テクノロジーの開発をしている企業を対象としたシンポジウムで、昨年度開催した第1回は大変好評をいただき、2024年11月6日(水)に第2回の開催をすることになりました。
本シンポジウムを通じ、新しい発想・アイデアとテクノロジーを介護分野で活用していくことや、開発企業単体では把握しきれない介護現場のニーズや介護現場での実証評価について気付きを得ること、介護現場に対する疑問や課題解決につなげることを目指すことを開催の目的としています。
今回は、このシンポジウムについてライターの白石が印象に残った内容を中心にお伝えさせていただきます。
―内容―
セッション1 「2030年から問う介護」
介護テクノロジーが実装された介護現場はどうなっているでしょうか。
今回、2030 年という少し先の、でもそう遠くない未来の介護現場の模型を開発しました。模型を見学した介護事業者からいただいた意見を共有しながら、共同パートナーとFCL副所長の芳賀が共にトークセッションに登壇しました。
*Future Care Lab in Japanでは、「介護テクノロジーの実装」を単に介護現場にテクノロジーを導入ということではなく、「介護テクノロジーが業務オペレーションに組み込まれ、活用を継続し続けられること」と、考えています。
テーマ1「ひろがる、介護施設の可能性~開かれた介護施設へ~」 について
地域や社会と連携することによって、介護サービス以外の企業の方や、人々が介護に関わる可能性を広げることはできないか。開かれた介護施設とは、東北大学の平田教授にお話をいただきました。
冒頭、芳賀よりFuture Care Lab in Japanでは、「介護テクノロジー」を「最新技術に限らず介護現場のニーズに応じて、要介護者・介護者の生活を向上させ、活用し続けられる技術レベルの道具(福祉用具・ロボット・センサー・システム・AI等)や、その環境整備」と定義していると話をしました。
平田教授が、『最新の技術だけでなく、既存の技術をいかに結合していくという所から、新しいイノベーションが起こるのではないか。それぞれの人が「こういう社会をつくりたい」「こういう介護施設を作りたい」等、想いを共有できることで、あらゆる方向からアプローチしたとしても最後は一つのところに集約できることで、健常者も障がい者もわくわくするような環境を作ること』とおっしゃっていたことがとても印象に残りました。
技術やテクノロジーそのものではなく、まずはそれを使う人がどう考えるのかが大切だと感じました。
テーマ2「快適な暮らしを、考える~居室は寝るだけの場所から、趣味や人との団らんの場所にもなる~」 について
お一人おひとりの過ごし方に合わせた、本当の意味での生活の質を高める居室の環境について、パラマウントベッド株式会社の野口さまにベッドの開発経緯含めお話しをいただきました。
『介護環境はあらゆる人にとって「自分らしく」「楽しく」いられる場であること。日々のなんとなく感じている違和感や、介護業界の常識によって諦めてしまっている可能性みたいなものを拾い集めて可視化し、改善を繰り返すことによって介護する側、介護される側ともに、より良い環境になっていく』とお話されていました。
-1024x382.jpg) ベッドがソファーになることで、居室を寝るだけの場所からくつろぎの空間へ
ベッドがソファーになることで、居室を寝るだけの場所からくつろぎの空間へ
私自身、介護現場で長く働いていましたが、ご利用者さまの居室にベッドが存在することに違和感を持ったことはありませんでした。今回の話を聞いて「ベッドがあるから横になりたくなってしまうのだな」と気がつき、改めて当たり前は当たり前ではないことから考えてみようと思いました。
テーマ3「職員が記録しない介護記録~記録するための業務時間を極限まで減らす~」
介護記録を見直すところから始める業務の改善について、株式会社ブライト・ヴィーの 飯田さまからシステムの開発経緯含めお話しをいただきました。
『介護現場に聞くと、なぜ記録するのか、誰のために記録しているのか分からないまま記録していて、それを考える余裕がないのが現場の現状としてあるようだ。記録し過ぎていないか、本当に必要な記録は何かを整理したうえで、センサーなどを活用しながらしっかりと記録を取れていく流れができれば、明日の介護がよくなるような分析結果が出てくるとか、AIから提案が受けられるようになる』
ということを伺い、本来、介護現場で働いている我々が、きっかけとなり提案していかなければならなかったと感じました。
テーマ4「働き手はどんな職場を選ぶか?~負担を軽減しながら働ける職場環境~」
最適なパフォーマンスを発揮できる、魅力的な職場の環境について、社会福祉法人若竹大寿会の山岡さまにお話しをいただきました。
『これからの介護業界の生き残りは、利用者に選ばれることよりも、スタッフに選ばれることが勝負。「わくわく感」「楽しい介護」そういった観点がすごく大事。介護する側、介護される側も「いい介護」をされたいわけではなく「介護されたくない」と考えている中で、
自分で「どういう将来」「どういう介護の世界」「どういう風に生活するか」を選択するのかをそれぞれが思い描くことで、そこに「わくわく感」をもって共に取り組めたらいいし、一人でも多くの人の「笑顔」が増えていくように取り組んでいきたい』と、お話されていたことが印象に残っています。
私も、これから一緒に働き続ける職員と一緒にどういう職場であれば良いか考えるきっかけになりました。
セッション2 「開発企業とFuture Care Lab in Japanの取り組み事例 ~サービス付き高齢者向け住宅安否確認システムの開発~」
 介護現場のニーズと開発企業が持つシーズをどうマッチングし製品をリリースしてきたのか、またFCLではどのようなサポートができるのかについて、Enazeal株式会社の畠山さまと研究員の丹野が製品開発に取り組んだ事例をご紹介しました。
介護現場のニーズと開発企業が持つシーズをどうマッチングし製品をリリースしてきたのか、またFCLではどのようなサポートができるのかについて、Enazeal株式会社の畠山さまと研究員の丹野が製品開発に取り組んだ事例をご紹介しました。
Enazeal株式会社の「離設検知システム」で使用している画像解析技術を使用して、サービス付き高齢者向け住宅の「安否確認」をすることはできないかと考え、製品の開発に取り組みました。今後、SOMPOケアのサービス付き高齢者向け住宅にて検証をする予定になっています。
私は、今まで人だけに頼っていた安否確認に、システムを併用することにより、ご利用者さま・ご家族さまと職員が安心して業務ができることにつながると感じました。
シンポジウムには、会場でのリアル参加とオンライン参加がありましたが、300名程の方々にご参加いただき盛況で終了することができました。
シンポジウムやそのあと開催された懇親会でも、多数の質問をいただき、開発企業さまの関心の高さを伺えました。
次回は「腰痛可視化ツール」についてご紹介します。